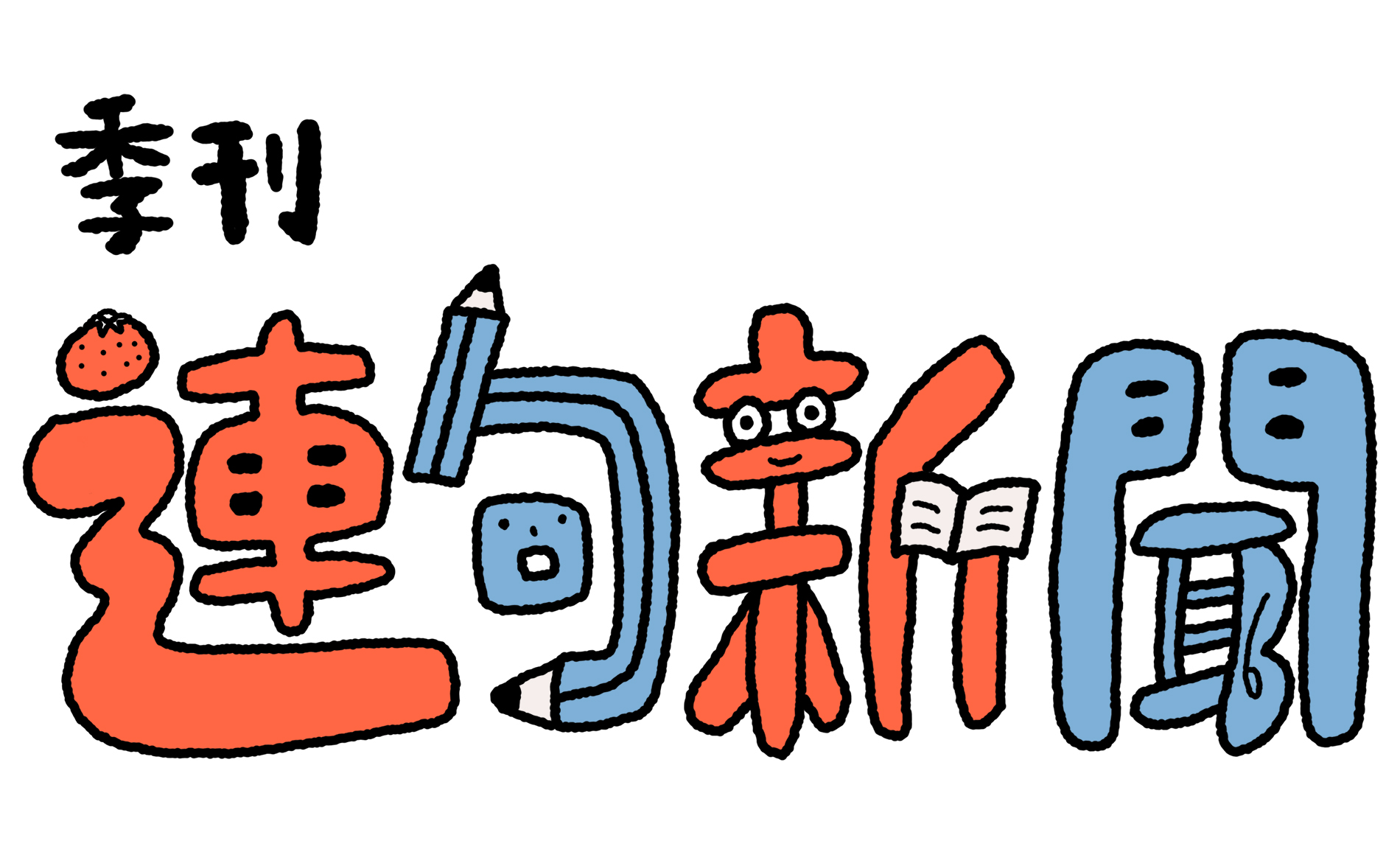第1回 第三は盛り上げ隊長
新企画「連句まめちしき座談会」発行人の高松と門野が連句についておしゃべりします。
第1回目は「第三句」についておしゃべり。しょっぱなから大脱線していますが、ちゃんと戻りますので安心してくださいね。
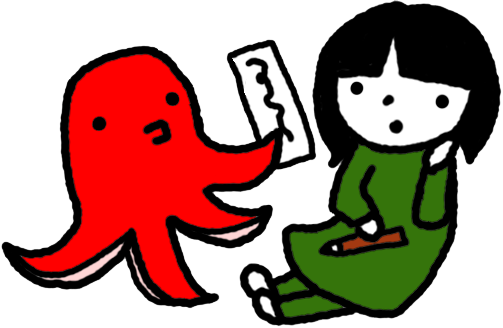
第三を知るには四句目から!?
高松 門野さん第三付けるの得意?
門野 そんなに得意じゃないかもしれないですね。高松さん第三の留め方についてはどう思いますか?
高松 私は四句目までを読まなきゃいけないと思っていて。四句目は、どこかに飛んでいってしまいそうな第三のサポートをしてる。たとえば猫蓑会の四句目まではこんな感じ。
木枯やたけにかくれてしづまりぬ 翁
時をりに舞ふ綿虫の群 林転石
少年の詩心ふつと湧くならん 本屋良子
シャープペンより2B鉛筆 武井雅子
門野 なるほど。
高松 発句で「こんにちは」、脇で「どうもこんにちは」、それだけでは話が終わってしまうので、第三が「それはそうとこんな話があります〜!」って飛び込んでくる。それを落ち着かせて、次に繋げるのが四句目。
門野 第三までで1セットって考えがちですが、あくまで四句目までで一つの流れを意識したほうがいいということですかね?
高松 そうそう。その次に、月前、月と来るので、「じゃあ四句目どうすれば?」って言われることがあるんですよね、初心者の方々からは。
門野 確かに連句人は四句目(しくめ)と言って、さらっと付けるのがいいと言うけど結構重要だったりする。はじめはなかなかニュアンスが掴みにくいと思いますが、先の猫蓑会の作品はいい例ですね。
高松 さらっと付けやすいんだけど、実は重要。
門野 月を控えているということもあるし、ここで一旦落ち着かせるみたいなイメージでしょうか。そうやって全体の流れを考えられると付けやすいですね。
高松 そうそう。付けやすいし、説明しやすい。宮城県連句協会の四句目までを引用しますね。
壺の碑に雪共に語らん蝦夷の誇り 狩野康子
滋味あふれる厳寒 永渕丹
賽の目に任せる援助の順番を 鵜飼桜千子
序曲はラ音から 康子
門野 うまいですね〜。こうやって四句目だけに注目して見ていくとおもしろい! どういう句がいいのかわかってきますね。
高松 ですよね!
門野 でも、第三特集なのに四句目の話してますね……。
高松 ああっ!

第三は「盛り上げ隊長」!
高松 第三むずいですよね……。どこまで飛ばしていいのか。表の制約もあるし。
門野 気持ち的には結構飛ばしていい気はするんですよね。発句と脇で寄り添って付けているので、その場の雰囲気としては「一気にそこから離れてみましょう~!」みたいな気持ちです。
高松 ですねですね、私も「発句と脇のことは忘れてください」って言いますね。盛り上げ隊長ですからね、第三は。
門野 盛り上げ隊長!
高松 盛り上げ隊長。連句は第三から展開するので。
門野 確かに!発句と脇で2人の世界観が出来上がっていますが、3人以上の座なら、第三が投入されることで、一気にそこからみんなの世界が広がっていく感じというか……盛り上げ隊長ですね!
高松さんは第三を付ける時、どんなことを考えて付けてますか? コツとかありますか?
高松 去年の桃雅会の第三もそうだけど、ぜんぜん違う景をつくること……かな……。
霜柱踏めば力を貰ひけり 杉山壽子
はるかに続く冬晴の丘 寺田重雄
新海苔をあぶり部屋中香の立ちて 高橋すなを
子供の開く絵本カラフル 中西靜子
門野 冬晴れの丘から、部屋の中で新海苔をあぶる景へ。
高松 なんかぜんぜん違うことしてる! ってなった。これは。
門野 ぜんぜん違いますね。でも隣り合った世界だと思う。部屋の窓から、冬晴れの丘が見えているのかな。
高松 そう。一瞬びっくりしますけどね。発句と脇が「同時同季同場所」だから、それと真逆って思うと楽だよね、条件的には。
門野 一瞬びっくりするけど、その世界の繋がりを見つけた時、「連句~!!」ってなりますね。
高松 春眠子さんは、納豆の糸のように繋がっている、と言ってましたね。
門野 まさに細い糸ですね。やっぱり第三から連句が始まるー! という感じですね。
高松 その、ウワーッって盛り上がっているところを、四句目で「落ち着け」ってやる感じ。ツッコミとボケみたいな。
門野 第三と四句目の関係性、尊いですね。四句目、にくい奴!
✩次回2025年夏号は、「月の座」についておしゃべりします!