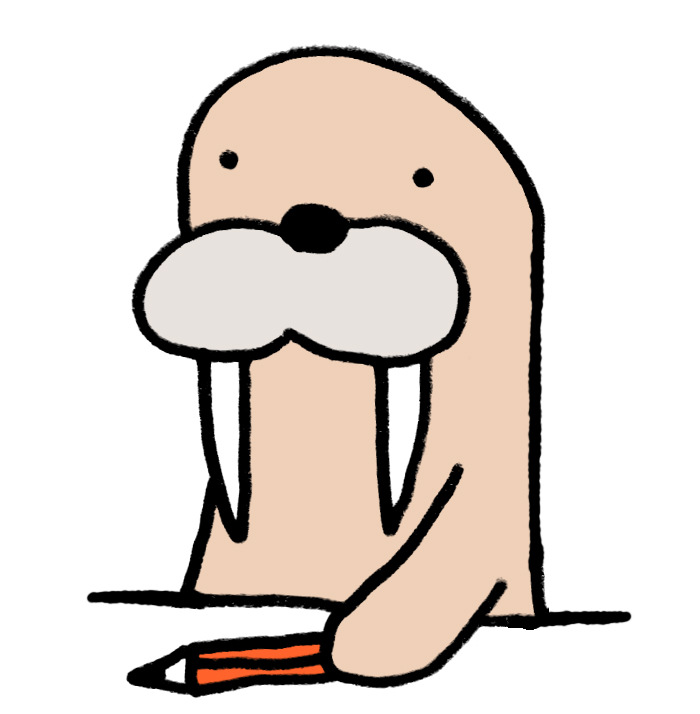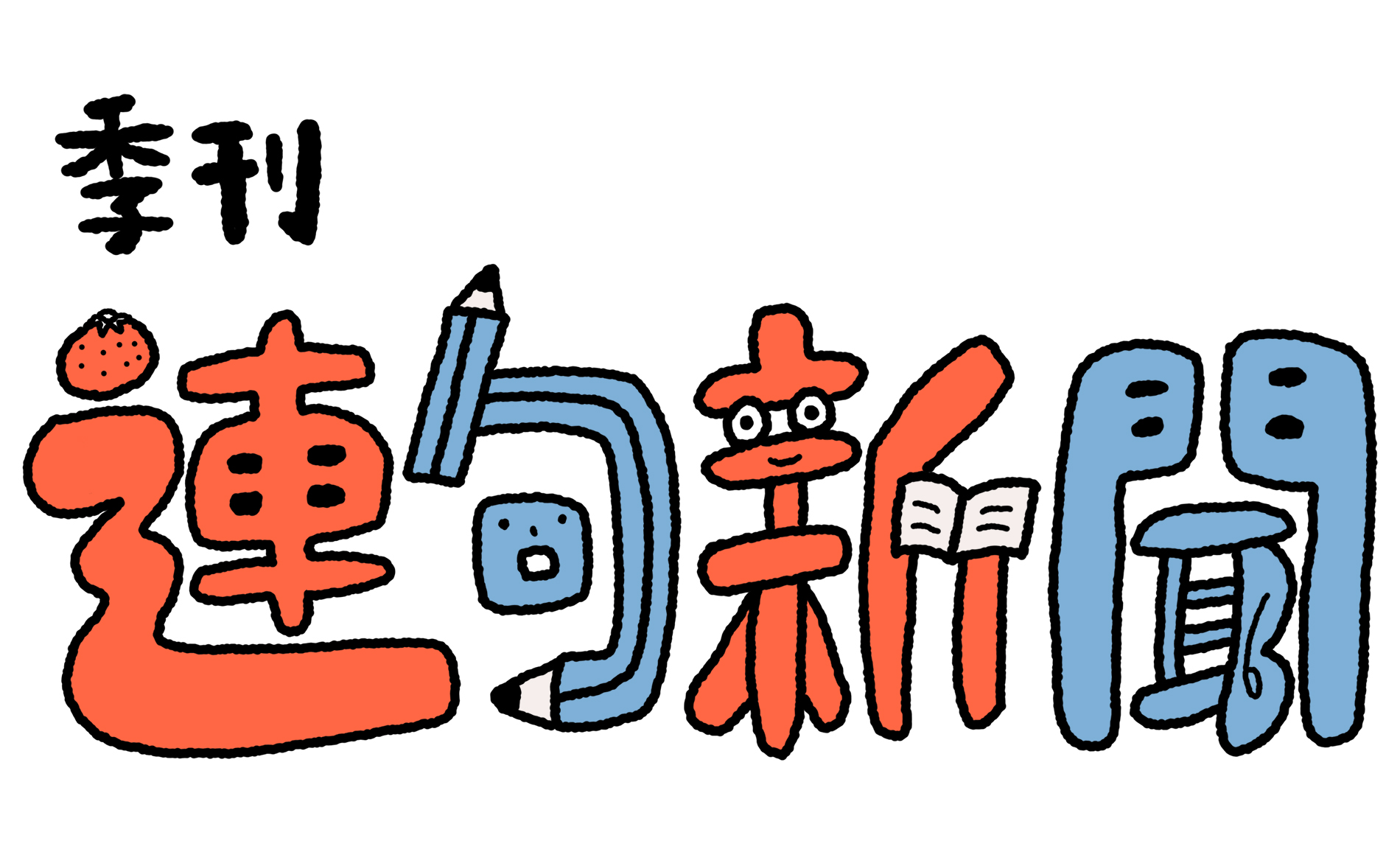変容する連句 堀田季何
連句は変容しつつある。
こう書くと、専門連句人の何割かは眉を顰めるに違いない。どういう意味だと。連句は常に時事や現代語を取り入れてきているが、それは新しさとは違うし、況して変容とは言わない。最近の連句本でも、そこに書かれている式目は、何十年前の連句本のそれとはほぼ変わらない。形式にしても、新しいものはたまに生まれるが、歌仙、短歌行、半歌仙が相変わらず多い。では、こう書こう。
連句は変容しつつある。少なくとも、流行は変わりつつある。
これならもう少しわかりやすい。宗鑑や守武の頃の初期の俳諧、貞徳を盟主とする貞門俳諧、宗因らの談林俳諧、芭蕉らの蕉風俳諧など、俳風の勃興と変遷は歴史的にある。筆者が指摘したいのは、目下、新しい俳風が広まりつつあるということである。しかし、厄介なのは、それが広まりつつあるのは、日本連句協会、連句結社、(今も続いている)宗匠俳諧などを軸とした連句界でなく(本文では、その連句界に身を置いている人間を専門連句人と呼ぶ)、それ以外の文芸家や愛好者の間である。つまり、連句界では変容は特段見られないが、それ以外の場所で変容しつつあるということだ。
その変容の芽は百年くらい前から存在する。それは、連句の隣の世界の住人たち、すなわち俳人、歌人、詩人、小説家といった人間が連句人抜きに時折連句を嗜んだ記録である。それも、連句的には「失敗」「下手」と言える類のものである。正岡子規は、宗匠の宇都宮夢大や連句人と言って差し支えのない寺田寅彦(TORSO形式の考案者)とだけでなく、他にも記録を残しているが、その中で一番名高い、高浜虚子との両吟は、お世辞にも上手いとは言えない。付け句の付け方がワンパターン、転じ方は小幅、打越気味、去嫌はほぼ無視で、ずっと同じ世界にとどまっているかのようである。その虚子が夏目漱石及び坂本四方太(ホトトギス選者)と巻いた三吟も、同様の問題が散見され、暗澹となる出来だ。
もう少し後の時代、柳田國男と折口信夫の両吟は、別の意味で連句的問題が発生する。ひたすら二人の共通の博識(古典の知識にしても、大昔の教養人のレベルであって、現代人が通常持っているレベルを凌駕する)をベースに付けていくので、座の文学とはいえ、第三者がそのまま理解するのは至難である。当然、付け方はワンパターンになるし、典拠をベースに付けていくと転じ方は弱くなり、似た味わいの句が並ぶのは必然である。また、一句一句凝りすぎるあまり、全体の構成やバランスに対する目配りが弱くなっている。
以後、大岡信、岡野弘彦、丸谷才一の作品、辻原登、永田和宏、長谷川櫂の作品にせよ、岡野弘彦、三浦雅士、長谷川櫂が谷川俊太郎、三角みづ紀、蜂飼耳、小島ゆかりを客人に迎えて巻いたいくつかの作品にせよ、笹公人、俵万智、矢吹申彦、和田誠の作品にせよ、上述の諸問題を孕んでいる。その上、平句なのに詩的飛躍や捻りや切れが強くて発句らしくなっていたり、立花北枝以降の人情の句(自、他、自他半)と人情無しの句(場)に対する打越の配慮も弱かったりする。さらに、全体に資する句を付けるという概念が稀薄で、前の句に対して最上の句を付けるという概念が支配的である。全体を見て付け方や転じ方を調整するとか、軽く詠むとか、さらに軽いやり句(逃句)を入れるとか、そういうことがない。一句一句が主張の強い句になり、従来は一巻の一、二割で十分な「見せる句」が徹頭徹尾占めるようになってしまい、結果、序破急や暴れ所は目立たない。任意の二、三句の並びを見ても、歌仙のどのへんなのか判らない場合が多い。それに、前の句に対して最上の句を付けるという概念を徹底すると、発句と脇句くらいの距離の付けが頻繁に起き、あまり転じなくなってしまう。
しかし、従来の連句観から指摘されるこのような文人俳諧(と便宜上名付けておく)の弱さは、弱さとは言い切れなくなっている。それどころか、強さになりつつある。それには二つ理由がある。一つは、別の価値観ないし新たな俳風だと割り切れる可能性があること。ひたすら一つの世界に居続けるように、全体のトーンが揃い、一句ずつの付けが凝っていて、一句一句が「見せる句」になっている作品は、それはそれで良いのではないだろうか。これは、開き直りではない。座の文芸というものを純粋化すれば、その座が一体となった一つの純粋な作品に行きつくのは当然の帰結である。多様な世界を航海する冒険譚をやめて、一つの世界観を持つ短い現代詩を書くようなものである。窮極的には、数種類の大きさと色のダイアモンドを三十六個美しく散りばめて宝飾品を作る感じと言えよう。そう思えば、これまで列挙してきたような短所は長所に様変わりする。もう一つは、こちらの方が人口に膾炙したということだ。現在、商業的に流通している作品は、前述の大岡信から笹公人までの作品であり、いわゆる連句人の作品ではない。商業ジャーナリズムと言えばそれまでだが、書店で、歌仙が載った本を買おうとすると、著名な文人たちによる作品集ということになるし、否応なしに、それが一種の模範になる。実店舗の大型書店でもアマゾンでも、目にするのは彼らの作品集であり、彼らの(俳句、短歌、自由詩、小説の)ファンが連句を知る入口になり、その一部が自分自身で歌仙を巻き始める時の模範ないしサンプルとして機能する。筆者には残念なことだが、東明雅ほど高名だった連句人兼俳文学者の作品でさえ、書店ではさほど出回っていない。これは、商業の原理が連句界と無関係にもたらした流行であり、その流行における連句の在り方が人口に膾炙しているということは、連句人がどう思っても、文人俳諧の俳風が主流になりつつある、連句は変容しつつあると考えるのは不思議ではない。連句結社的(専門連句人的)な連句と文人俳諧的な連句に根本的な断絶がある中、前者が不易のまま、後者の流行が現代の俳風となりつつあるのだ。
実際、筆者の周辺にいる連句界の住人たち、いわゆる専門連句人と話すと、文人俳諧の評判は芳しくない。連句の普及には役立っているけど、間違えた形で連句が伝えられている、本当の連句を伝えたい、と彼らは危惧している。ただ、筆者自身が、専門連句人以外とも連句を楽しみ、時折、文人俳諧的な連句を嗜む捌や連衆たちと作品を巻くときに思ったのは、文人俳諧的な連句も悪くないな、捌や連衆次第では非常に美しい世界を構築できるのだな、別の価値観だと割り切ることができれば、こういう連句が広まるのもアリだな、と。
無論、筆者自身がリアルで捌くときは(リアルの方がオンラインよりも遥かに捌きやすいし、連衆に要望を伝えやすい)、連句結社的な連句に近い形で行っている。商業的に負けているとはいえ、芸術性は文人俳諧的な連句に優るとも劣らないのだし、慣れていることが大きい。但し、文人俳諧的な連句の会にもどんどん参加してみようと思っているし、そういう会もいつか捌いてみたい。
最後に、筆者の予感だが、連句結社的な連句にせよ文人俳諧的な連句にせよ、連句というものは、いつかは変容という言葉では済まないくらい激しい、包括的なパラダイム・シフトに遭遇する。その時は、式目そのものが揺れるだろうし、連句という詩型の定義や範囲さえも安全ではいられないだろう。変容云々と言っていられるのは、それまでのことなのかもしれない。
堀田季何(ほった・きか)
俳人、歌人。「楽園」主宰、「短歌」同人、「扉のない鍵」別人。句集『亞剌比亞』、歌集『惑亂』他。