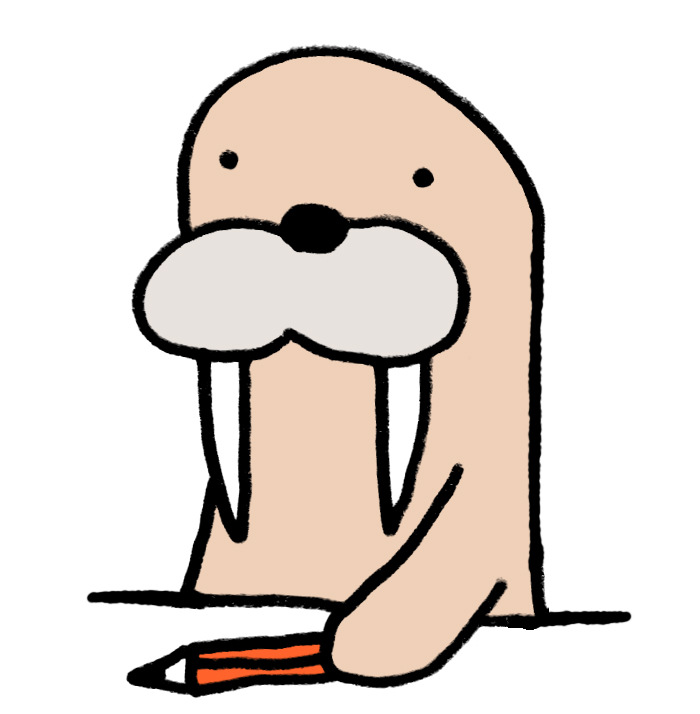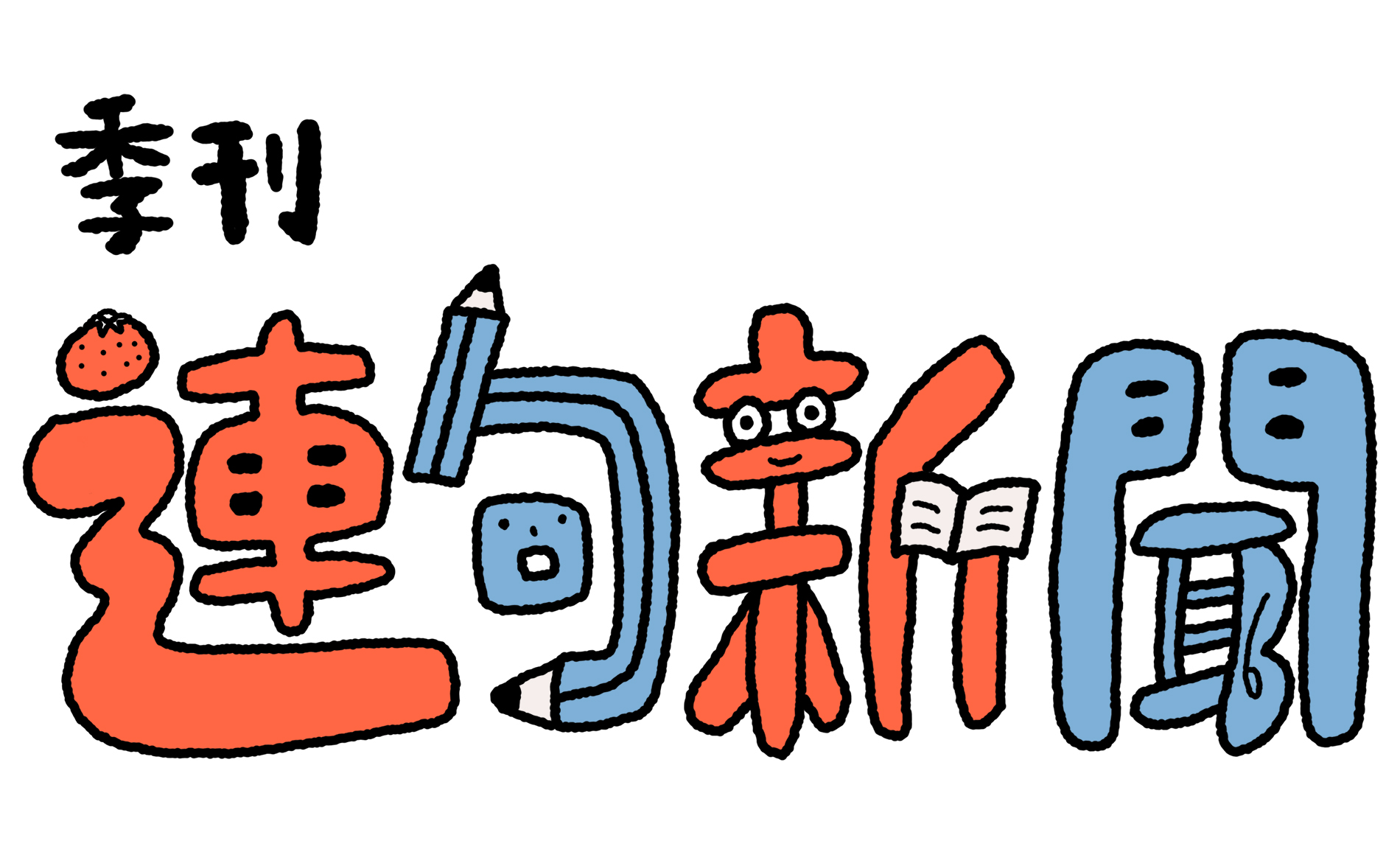かっこいいムカデみたい 暮田真名
定型詩が不自由だというのは嘘だ。
川柳を書きはじめてから特にそう思うようになった。句を作るとき、わたしはただ五七五におさまるように言葉を並べているのではない。川柳定型は単なる枷ではない。川柳は私と一緒に書いてくれるのだ。どこまで私が書き、どこから川柳が書くか、負担する分量は場合によるが、わたしは句を自分ひとりの力で書いたことは一度もないと断言できる。
定型詩をやめて自由詩を書け、なんて、一人で走ったほうが速いから二人三脚という競技自体をなくしてしまえ、というようなものだ。たしかに二人三脚よりは一人で走ったほうが速いかもしれないが、それはわたしが遅いからだ。川柳はわたしよりもずっと速い。本当は川柳だけで走るのがいちばん速いのだが、川柳はなぜか自分だけで走ろうとはしない。謙虚なのか、あるいはわたしとおなじなまけものなのか。しかたなくわたしも走る。
これから二人三脚の例えを連句に持ち込もうと思う。
連句の話をする前に、まずは俳句の話をしなければいけない。いままでに二、三度連句の座にお邪魔したことがあるが、いずれの機会も歳時記が必要だったので、わたしは連句を「俳句寄りの文芸」と認識している。
川柳は「わたしと川柳だけ」で走り出すことができるが、俳句は「わたしと俳句だけ」というわけにはいかないようだ。俳句は季語を連れてくる(ことが多い)。季語は無数の足を伴ってやってくる。俳句と走る生者たちの、その数を軽くしのぐ俳句と走った死者たちの、無数の足……。
歳時記を携え、見えない足がぞろぞろと蠢くのを感じていると、連句の座には生身の人間たちが集まってくる。当然のことながら、連句も「わたしと連句だけ」で走り出すことはできないのだ。
「わたし+連句+座を共にする連衆の方々+季語+連句のふくざつなルールを作り上げたであろう過去の連句人たち」……。
いま、足は何本ありますか?
連句はムカデのようなものかもしれないと思うし、わたしはムカデの足の一本としてスマートに振る舞えたためしがない。最初はあんなに威勢がいいことをいっていたわたしも、連句の座に加わるときはたしかに「不自由」を感じてしまう。連句を巻くとき、わたしひとりに書けることは川柳を書くときよりもさらに少なくて、それはなまけもののわたしにとってはありがたいことであるはずなのに。
とにかく連句はわたしを戸惑わせつづけている。人を戸惑わせるものはかっこいい。
暮田真名(くれだ・まな)
川柳人。1997年生。句集『ふりょの星』(左右社)発売中。
「川柳句会こんとん」主宰、歌人の大橋なぎ咲さんとのユニット「当たり」など。