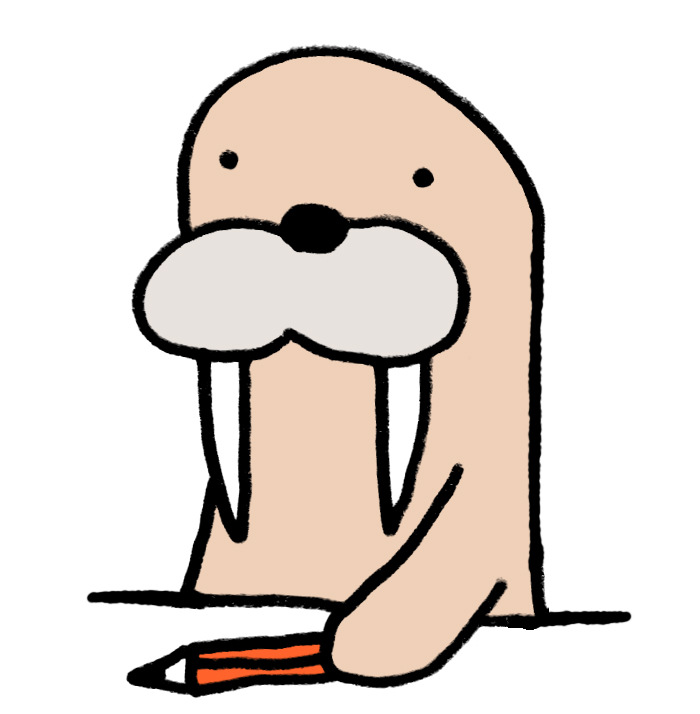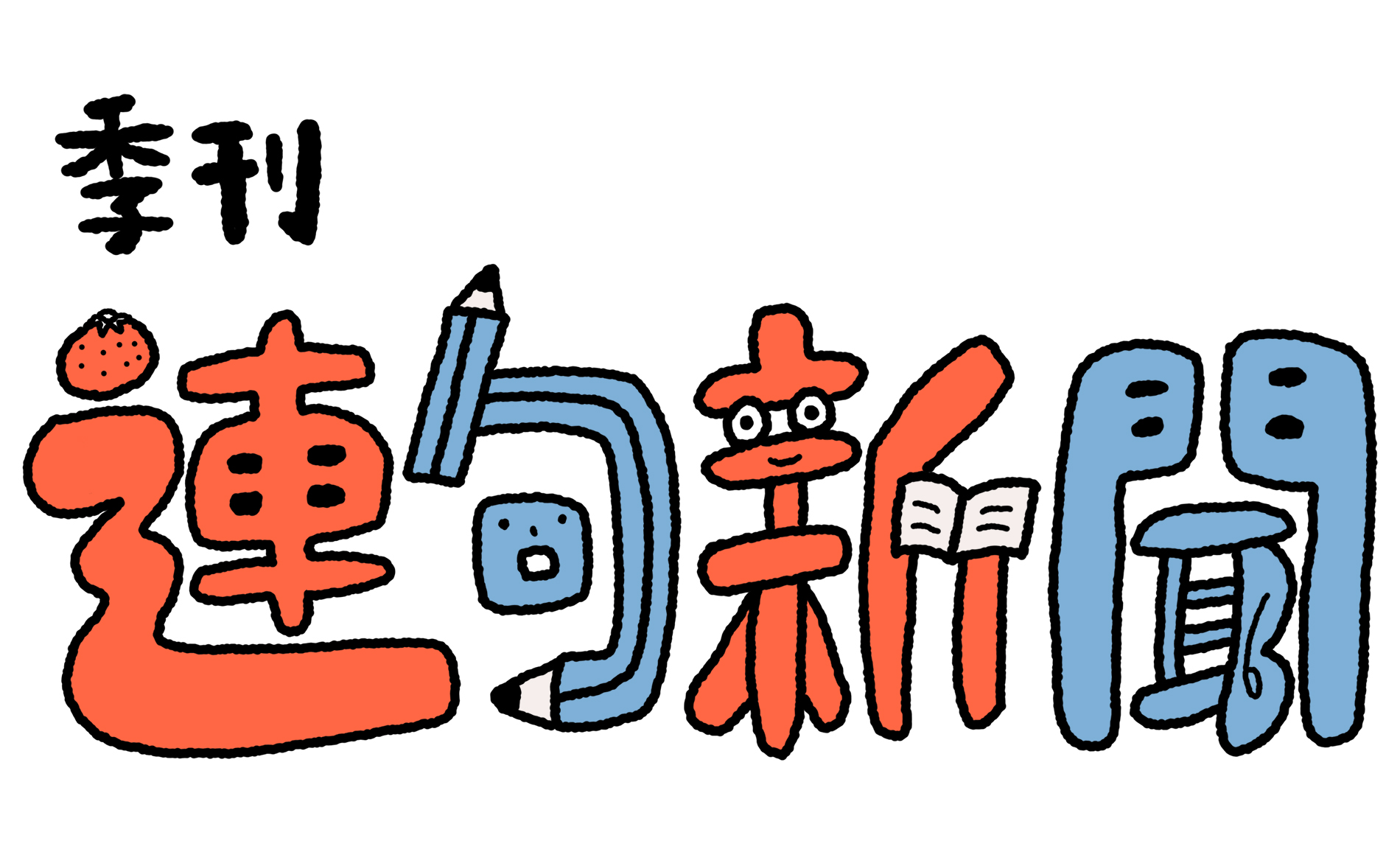蜃気楼 福田若之
連句という名にも、いまとなってはそれなりの由緒がある。たとえば、虚子がこの名を採った理由は、彼の「連句論」の冒頭に詳しく書かれている。けれど、僕にとって、この名はあまりに味気ない。その字面が、たんに句が連なったというだけのもの、という印象をもたらすからだ。連句という名を枕に据えてみても、僕にはどうも夢みることができそうにない。
俳諧という古い名を、ふたたび書きおこすことにしよう。俳諧とは、まさしくそう呼ばれるものの味を表す言葉だった。
俳諧連歌を俳諧と略するのと、それを連句と呼びかえるのではずいぶん違う。俳諧という名には、長短の繰り返しが生みだす律動を歌と捉える意が、言葉としては略されながらも、あらかじめ含みこまれている。対して、連句という名は、長句と短句の連なりをかたちとして捉えるばかりで、あたかも、どれほど連なろうとも句は句にすぎないかのようだ。もしそうだとしたら、長短を繰り返さずとも、ただ句を横並びに連ねればよいことになってしまうわけで、いわゆる連句の座にあっても、僕としては俳諧をしているつもりでいる。
『誹諧御傘』の序に「抑はじめは誹諧と連歌のわいだめなし」といい、『三冊子』に「俳諧は歌也」という。百韻といい歌仙というのも、そもそもは俳諧を歌とみなしていたからこそのことだろう。連歌という名のもとでなら、いくら千句だの万句だのと称しても、それで総体としての歌の意が損なわれることはない。しかし、連句という名は、一見そのかたちを的確に言いあらわしているようでいながら、肝心のことを忘れさせてしまいかねない危うさがあるように思う。
たとえば、『郷愁の詩人 与謝蕪村』の萩原朔太郎は、蕪村の「春風馬堤曲」を評しながら、「単に同一主題の俳句を並べた「連作」という形式や、一つの主題からヴァリエーション的に発展して行く「連句」という形式やは、普通に昔からあったけれども、俳句と漢詩を接続して、一篇の新体詩を作ったのは、全く蕪村の新しい創案である」と書いている。歴史認識の正否についてはさておき、朔太郎ほどの詩人が「連句」を俳句の「連作」と並ぶ一形式にすぎないものとしてこんなふうにあっさり片付けてしまったのもまた、ひとえにこの名ゆえのことではなかったか。
連句という名と違って、俳諧という名は歌の夢へと僕をいざなう。とりわけ連歌が他の和歌と違うのは、なによりまず、それが巻かれるということだろう。本来の連歌と同じく、俳諧もまた巻かれる。実際、式目が複雑なこともあって、すくなくともかつては適当な長さの紙に書きつけられることなしにはほぼ成り立ちえないものだった。俳諧という名は、巻かれる歌の夢、あるいはまた、紙のうえに歌うことの夢へと通じる。
『篇突』に「師ノ云、徘諧は文台上にある中とおもふべし。文台をおろすと、ふる反古と心得べしといへり」といい、『三冊子』に「思ふ事速にいひ出て、爰に至て迷ふ念なし。文台引き下ロせば即反故也、ときびしく示さるゝ詞も有」というのも、紙のうえに歌うというあの逆説を全うするための教えと読める。紙の歌が、歌としてみずからを全うするためには、言葉を迷うわけにいかない。そして、文台から下ろされるや否や、声の歌が谺のうちに消えてしまうように、ただちに反故とみなされなければならない。
『三冊子』にも「たとへバ歌仙は三十六歩也。一歩も跡に帰る心なし。行にしたがひ心の改ハ、たゞ先にゆく心なれバ也」とあるように、俳諧は連歌の一体として、帰らず先にゆこうとする。そのつど、前の付け合いとは別の光を見ようとする。覚えつつ忘れてゆき、その果てに反故になる。刻々と描きかえられながら、ついには掃き清められてしまう砂の絵のことを思う。ここにまたひとつの夢がある。さまざまの光の果てに、ついに書きあげられたものが、たちまちに反故になることの夢だ。つまり、蕩尽の夢。この夢がまず僕に与えてくれるのは、あの比類ない恍惚だ。しかし、それだけではない。遺された反故を眺めなおすことにもまた、夜の焚き火の跡を昼の河原に見るときのような、さびしくもうっとりとした気分がある。だからこそ、俳諧師たちは反故にあれほど手を入れたのだろう。巻かれる歌を夢みるにあたって、たんに連歌というのではなく、とりわけ俳諧が僕にとって望ましいのは、蕉門に伝わるこうした教えによるところが大きい。
ところで、発句はそれだけでは歌に満たない。それは、五にせよ七にせよ、せめてもう一節つかないことには、歌の体をなさないだろう。歌のはじまりをなすものが、それだけではまだ歌になりきっていない。俳諧を夢みるというのは、それとともに、こうした歌未満のかたちとしての俳諧の発句を夢みることでもある。だから、俳諧の夢は発句の夢の鏡ともいえる。紙のうえに歌うこと、そしてまた、さまざまの光の果てに、ついに書きあげられたものが、たちまち反故になることからなる俳諧の夢は、紙のうえに歌未満に踏みとどまること、それでもやがては反故になることの夢を、発句ならではのものとして映しだす。発句ではなく付合から生じた川柳というかたちには、いますこし違った夢があるはずだ。
俳諧のうちに発句を夢みて、発句のうちに俳諧を夢みる。この大蛤の合わせ鏡のうちに、またいくつもの夢が生じてきて、僕はまだ、いびきの漏れた海のかなたに、ただ楼の高みをまぼろしするばかりだ。
福田若之(ふくだ・わかゆき)
1991年東京生まれ。「群青」、「オルガン」に参加。第1句集、『自生地』(東京四季出版、2017年)にて第6回与謝蕪村賞新人賞受賞。第2句集、『二つ折りにされた二枚の紙と二つの留め金からなる一冊の蝶』(私家版、2017年)。