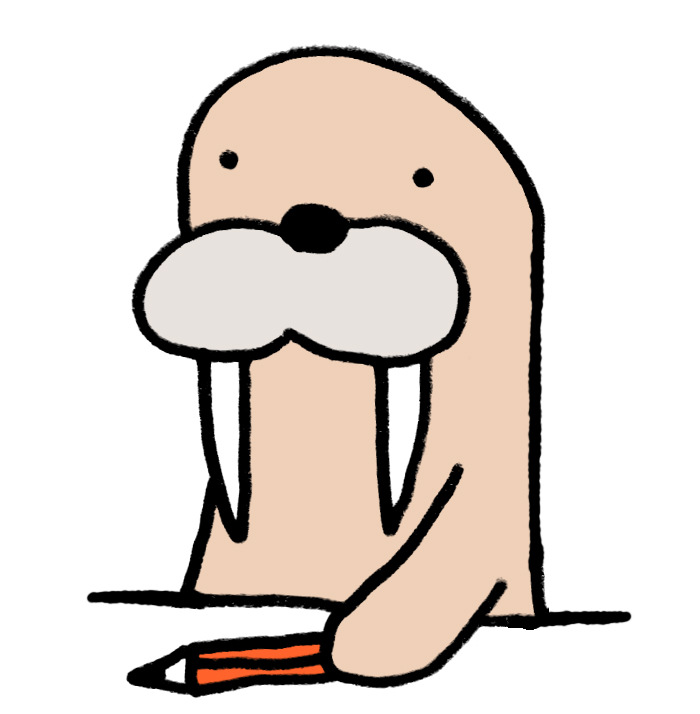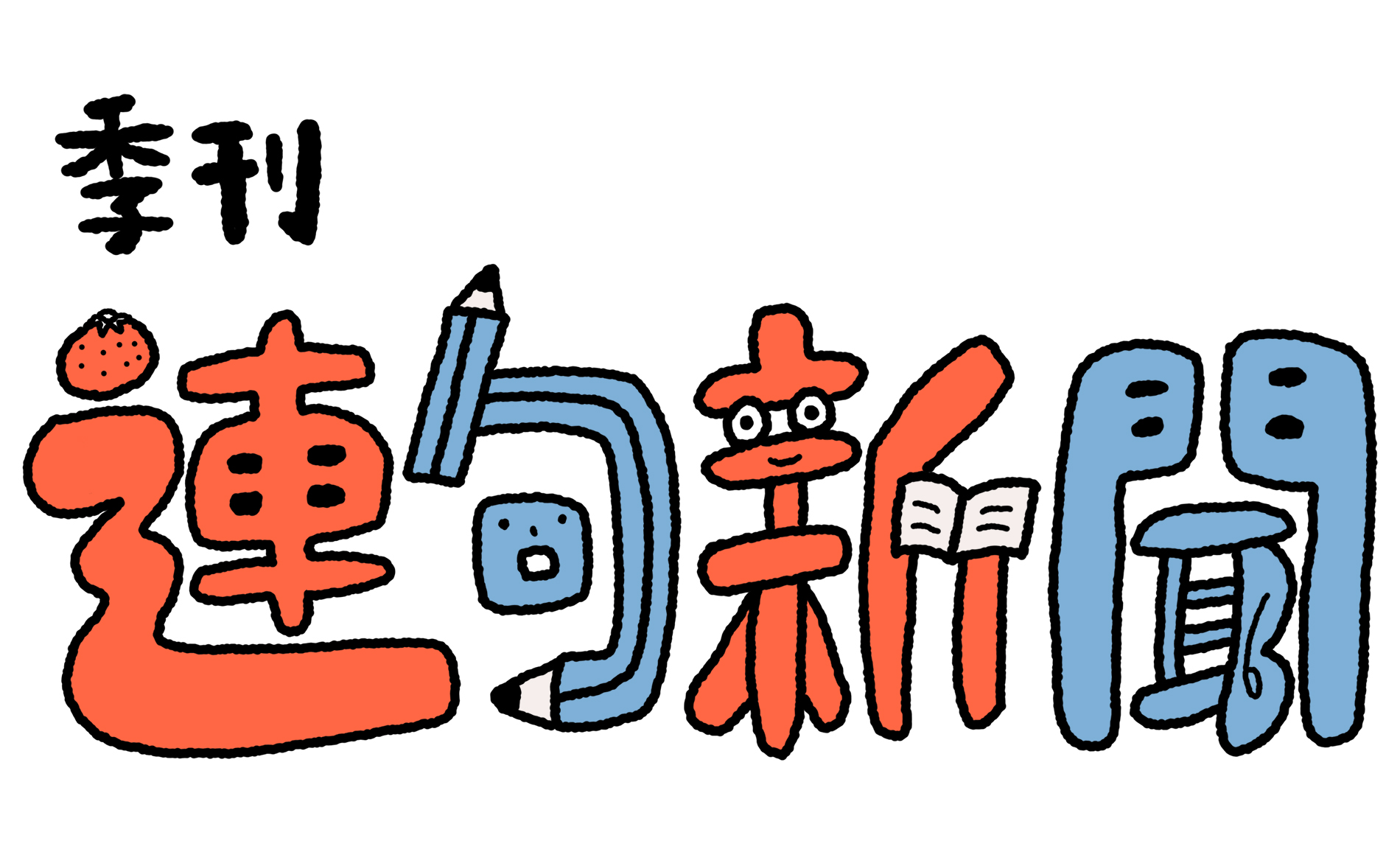という名の爆弾 大塚凱
見よう見まねで連句の捌をやったことがあるのだけれども、これがまあ、捌というのは差合見などとはまったく訳が違うというか、なかなかに骨が折れた。
さて、平素から連句をやっている人間は座を共にしていなかったので、私の力不足であたかも「猿連句」という風情になってしまったけれども、そのあとがまずかった。自分の勉強のために、と連句に心得のある人に私信でお見せしたのだが、直後にその方がTwitterで、あくまで匿名的ではあるものの、その連句についてコメントを書いた。私もマナーとして他人に見せるということは事前に伝えていなかったから、その投稿を見た連衆に行いを批判された。自らの捌き方について意見を仰ごうという気持ちで勇み足を出してしまった一方で、連衆は「捌に勝手に未公開作を公開され、ツイートに利用された」と感じることになってしまったのだ。これは偏に、無意識に「自分の作品」かのように取り扱ってしまい、事前の説明と配慮を欠いた私の至らなさによるものだったと思うから、反省している。
しかし、おそらく俳句ではこのようなことは、他人の未公開句の公開などのトラブルを除けば、なかなか起こりづらいことだと思う。
そのことがあってから「連句は誰のものか」ということを強く意識せざるを得なくなった。というか「連句において捌は何を引き受けているのか」を考えている。
ふと、芭蕉の死に際を思い出す。元禄七年(1694年)に江戸を発った芭蕉は西を目指し大坂で帰らぬ人となるが、その最後の旅に芭蕉を突き動かす一因となったのが、蕉門の分裂だったのだろう。例えば名古屋では、晩年の芭蕉が進めた「かるみ」の方向性に対して批判を強めていた弟子の荷兮を訪れた。ベテランの荷兮には、彼なりに自らの信じる俳諧があったであろうからこそ、芭蕉に同調する名古屋蕉門の露川との対立は深刻だった。
世は旅に代かく小田の行戻り 芭蕉
水鶏の道にわたすこば板 荷兮
その際の歌仙の発句。客人の芭蕉は「行戻り」と代掻きのさまを描写する。これは東海道を往復するにあたり度々訪れた荷兮への挨拶にも思える。荷兮との言葉の往還に成功したかどうか、この「世は旅に」の巻に交錯するものを読み解くにはまだまだ私の力量が足りないことが歯痒い。結局、芭蕉は失意を抱えたまま、更に西へ向かう。このとき、芭蕉が引き受けた苦しみは何だったであろうか。
他方、大坂でも、弟子の洒堂と之道が蕉門を分ける対立を深めていた。両者を交えようとする芭蕉の心労が、身体的な異変にも現れていたことだろう。自らの俳諧に対する追究が、蕉門という組織の崩壊に繋がった面もあったに違いない。この頃〈この秋は何で年よる雲に鳥〉と詠んだ芭蕉の旅路の果てにあったものは、それこそ雲間に鳥が消えてゆくような、虚無の思いだったのではないか。そのとき、それでも、芭蕉が座を統べる者としての役割を全うしようとしたこと。自らの名において、連衆の様々な立場を意識しながらも、一巻に筋を通すということの責任の重たさを思う。
責任を引き受けることこそが、”意志をもつことになっている”人間のみに出来うる、最後の営みなのではないか。これはきっと、銃にも、病原菌にも、人工知能にも、引き受けられない。人間のうちの、誰かが処理をしなければならない「爆弾」だ。〈旅に病んで夢は枯野をかけ廻る〉。枯野とは、「爆弾」がついに破裂してしまった、そんな焦土を思わせる。そして、かけ廻る速度は、重たい「爆弾」から自由になった、そんな芭蕉のあしどりを思わせる。
大塚凱(おおつか・がい)
一九九五年千葉生まれ。俳句同人誌「ねじまわし」を発行。イベントユニット「真空社」社員。 第七回石田波郷新人賞、第二回円錐新鋭作品賞夢前賞。共著に『天の川銀河発電所』(左右社、二〇一七年)、『新興俳句アンソロジー』(ふらんす堂、二〇一八年)、『AI研究者と俳人』(dZERO、二〇二二年)。歌人の阿波野巧也さんとPodcast「無責任な抒情」を月三回程度配信しています。