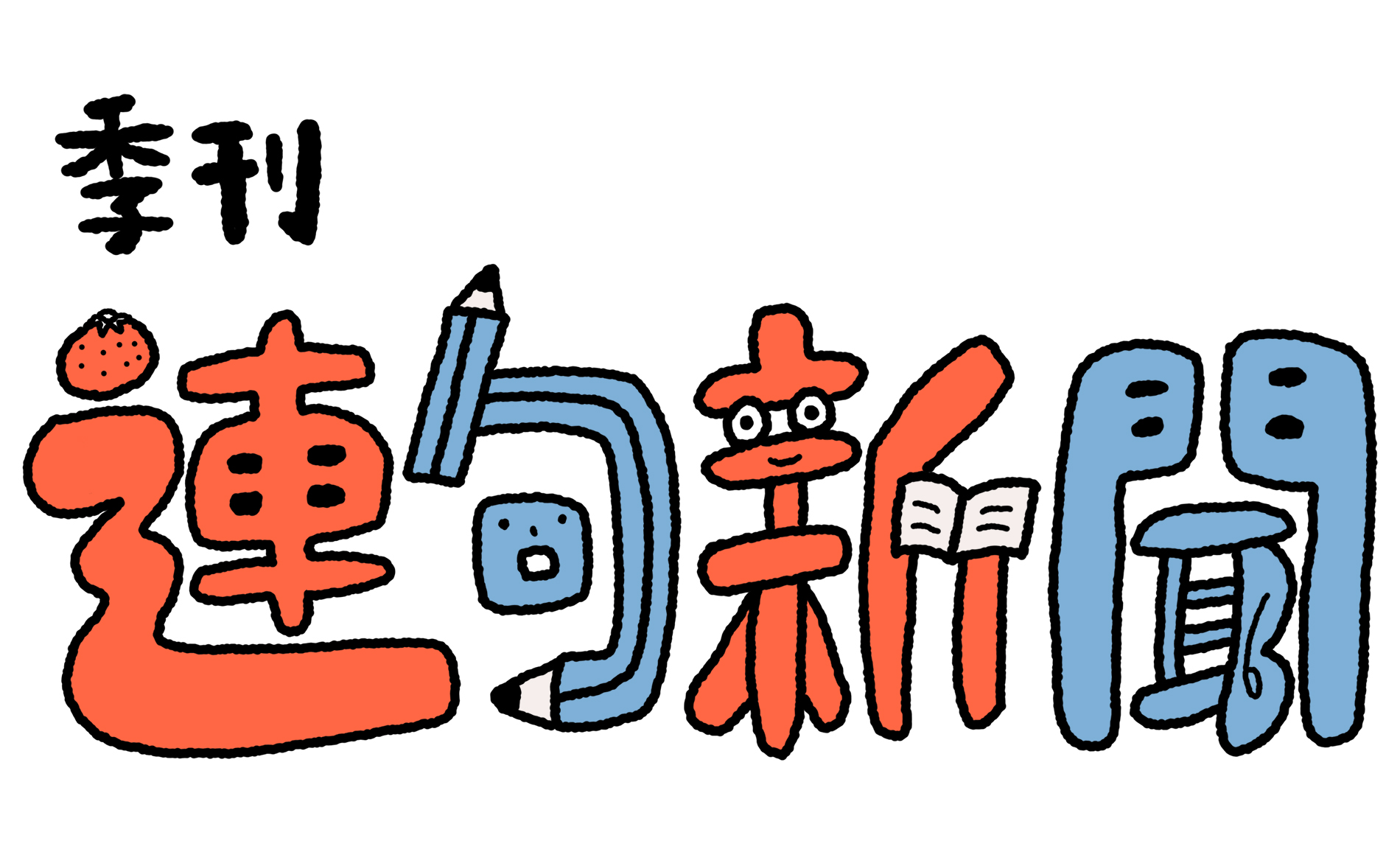連句は表現の宝箱 金川宏
日頃は主に短歌を詠んで暮らしているということもあって、連句と短歌を比較してみたり、連句から短歌に何か取り込めるものはないかと考えたりすることがよくあります。連句はアイデアの宝庫です。
耳を澄ます勇魚 瞑目するスワン わたしの春は白亜紀の遠火事
星の布置考えている 静かな生活 ジュラ紀の端っこで切手を舐める
昨年出版した拙歌集『アステリズム』から二首引いてみました。どちらも三つの句を繋ぎ合わせる構造になっていて、これは連句の「三句の渡り」からヒントを得たものです。「三句の渡り」を一首に凝縮できないかと考えたわけです。一首目は「勇魚」「スワン」「遠火事」と、三つの句それぞれに春の季語が入っています。文韻で自由律の歌仙を巻いているときに、考えた付句の案を組み合わせることを思いつきました。二首目はもともと「星の布置考えている」「ジュラ紀の端っこで切手を舐める」という二つのフレーズがあって、これを「三段なぞ」(Aと掛けてCと解く、そのこころはどちらもBだからという複式三段構えの謎かけ)で解いてみたものです。連句の「三句の渡り」はどこか「三段なぞ」の構造と似ています。さらに補足として、この二首について言及しておきますと、いずれも大幅な破調になっているということです。この「三句の渡り」を短歌の絶対律のなかに収めようとすると、内容が転じていても、韻律の力が働くのか、一首に意図しない結束性が生じてしまうんですね。破調のまま放りだしたほうがずっと響きがいい。これは新しい発見でした。以後定型を意識することがなくなりました。リズムは自分でつくりだせばよいのです。
みずのなかに繁っているのはひとのこえ饗宴すぎてウォルター・デ・ラ・メアの冬
同じ歌集からの引用です。この一首は、いわゆる短歌の〈私性〉からどれだけ遠ざかれるかを試みたものです(それにどれだけの意義があるのかは別問題として)。上句で少しずつ意味をずらしながら「饗宴すぎて」で大きく表現を変容させ、そこに収斂することなくさらに魅惑的な音韻を持った固有名詞に転じています。〈私〉に還ることなく意味を結ぶこともなくイメージは拡散したまま一首は終わります。連句をやっていると、俯瞰する眼を持ったり、自他場といって視点を入れ替えたり、それと対にして能動と受動を逆にしたりと、人称に関わる表現に自覚的になってきます。この一首はそのうえでさらに度合いを強めて人称のない世界へ繋がろうと試みたものです。自己などというものは、ほんとうは龍樹がいう「空」のようなもので、人は自分が何者かさえ知らないのではないか、という思いもあります。
このほかにも、連句には引き出すべき富がたくさんあると思います。今考えていることを少しだけ披露すると、作品を並べる時にリズミックな歌仙の形式を模倣できないかとか、歌仙一巻を短歌の連作に引き直せないか、とかそういった要するに遊び(ただし真剣な)ですね。連句はわたしの玩具箱であり宝箱なんです。ネット革命・AI革命がいわれ、情報が津波のように押し寄せて来る現在、顔の見える少数の仲間との繋がりを基本に置く連句がますますその存在感を高めていくことを願って、この稿をおくことにします。
◯ 金川宏(かながわ ひろし)
1953年、和歌山市に生まれる。現在も在住。
歌人。わかやま連句会代表。
2023年、第四歌集『アステリズム』(書肆侃侃房)を刊行。
X: @kanakana1226hi2